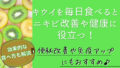栗は持って帰ったらこすり洗いをして水につける下処理をしましょう。
浮かんできたり、黒くなっていたり、小さい穴が開いている栗は虫が食べたか、中にまだ虫がいる可能性があるので捨てた方が良いです。
中から虫に栗を食べられないようにしばらく水につけるようにしましょう。
秋の味覚である栗はさつまいもと並んで人気のある食べ物です。
私も栗を食べるのが好きなのですが、皮をむくのが大変そうで、いつも剥いてある栗ばかり食べてしまいます。
そこで、今回はスーパーで買ったり栗拾いで採取してきた栗を調理する方法を調べました。
栗を水につけるという下処理の仕方から、面倒な皮むきを楽にする方法、保存法などを調べました。
これを読めばきっと、面倒だった栗の処理がいままでより楽になりますよ。
栗はこすり洗いした後水につけるのがベスト

買ってきたり、貰った、拾ってきた栗はしっかりこすり洗いをします。特に栗のお尻部分がでこぼこして汚れやすいので、入念に洗いましょう。
洗い終わったら半日から1日水につけます。長く水につけすぎると腐る原因になりますので、つけすぎないようにしてくださいね。
栗を水につける理由の一つは、とっても固い栗の鬼皮をやわらかくして剥きやすくするためです。
鬼皮は一番外の皮で、渋皮はその次にある薄い皮のことです。
私は初めて一人で梅干しを作った時に失敗してしまいました。
買ってきた梅の実をもう少しオレンジ色に熟成させたくなり、梅を一日水に浸したのですが、梅はすっかりぶよぶよになっていたのです。
その時は6月だったのが原因かもしれませんが、腐ったような臭いもし、その年の梅干しづくりは諦めました。
ですので、腐らないように栗も水のつけすぎに気を付けてくださいね。
栗を水につけるのは虫を追い出すためでもある

栗を水につけるのは、栗の中にいる虫を出すためでもあります。
スーパーで売っている栗は栗に入っている虫がそれ以上成長しないように、虫止めと言う作業をされていることが多いですが、拾った栗は中に虫がいる可能性があります。
ですので、まず栗をこすり洗いし、栗がつかるようにたっぷりの水を張ったボウルに栗を入れます。
半日から1日水につけると、水に浮いてくる栗があるかもしれません。それが虫が食べた栗です。
虫が食べて栗の中に空気が入っているため、水に浮かんでくるのです。
目視で虫を確認することは難しいのですが、妙に黒っぽい部分があったり、小さな穴が開いている栗も虫に食べられているものなので、捨てましょう。
選ぶと良い栗は、皮に艶や光沢がある、重みを感じる、丸みがあり粒が大きいものです。この3つで判断すれば美味しい栗をたべられますよ。
栗の虫止めをもっとしっかりしたいときは

栗を洗って水につけることで虫止め、とする場合が多いのですがもっと念入りに虫止めしたいという方は、下記の方法を参考にしてください。
【熱湯を使用した栗の虫止め方法】
- 大きめの鍋に水を入れ沸かす
- 湯が80℃くらいになったら栗を入れる
- 2分ほど茹でたら取り出す
- キッチンペーパー、布巾などで水気を拭く
これで虫の成長は止まり、中から栗を食べられる心配はなくなりました。私は、虫止めはもっと面倒なのかなと思っていました。
しかし、お湯で2分茹でるだけなのでコツもいりませんし簡単にできそうだと思いました。
栗は天日干しすると甘みが出てくる

栗はとれたてのものより、熟成させることで甘みが増します。私はなんでも新鮮なほうがおいしいに違いないと思っていましたので驚きました。
とれたての栗はまだ水分が残っており、天日に干すことによって甘みが凝縮します。
【栗の天日干しの手順】
- 買ってきたり拾ってきた栗はキッチンペーパーや布巾で汚れを落とす
- 良く晴れた日、太陽光に当たるような所で、新聞紙などの上に重ならないように栗を置く
- 半日から一日くらい干したらOK
- すぐ使わない場合は新聞と保存袋に入れて冷凍すると約6か月もつ
天日干しをする場合は、太陽の作用が虫止めの代わりになるので虫止めはしなくて大丈夫です。
天日に干すだけで甘くなるのはうれしいですね。
私は洗濯物を干したことを忘れるときがあるので、天日干した栗を家に入れることを忘れないようにしようと思います。
栗を長持ちさせるには常温より冷蔵庫が良い

栗は常温では日持ちしませんので冷蔵庫に入れるようにしましょう。しかし、冷蔵庫がいっぱいでもう入らないとなることもありますよね。
もし常温で保存したいのなら、鬼皮のついたままの栗を新聞紙に包みます。冷暗所において早く食べるようにしましょう。
鬼皮つきの栗と、剥いた栗の保存法をまとめました。
【鬼皮つきと剥き栗の保存期間】
| 鬼皮つき栗 | 剥いた栗 | |
| 常温 | 1週間 | 3日 |
| 冷蔵庫 | 1か月 | 3日 |
| 冷凍 | 6か月 | 3か月 |
剥いた栗は日持ちがしないので早めに食べきりましょう。
鬼皮つきの栗は、洗って水分を取ったのち、天日干しをして新聞、ポリ袋に入れて1か月もちます。剥いた栗は冷蔵庫でも3日くらいで食べきりましょう。
冷凍の場合は、鬼皮付きだと6か月、剥いた栗は3か月持ちます。
私は鬼皮つきで冷凍してしまうと、皮を剥く手間を考えて腐らせてしまいそうなので、皮を剥いてから冷凍しようと思います。
栗をもっと甘くする保存法は低温にあり!

テレビ番組で紹介された、栗を甘くする方法をご紹介します。
【栗が甘くなる保存法】
- 洗った栗の水気を丁寧に拭き取る。
- 新聞紙かキッチンペーパーで栗を包む。
- できれば透明なポリ袋か保存袋に入れる。
- 袋の口は閉じず少し折るくらいにする。
- 冷蔵庫のチルド室に入れ4週間寝かせる。
透明の袋がいいのは、新聞紙が湿ったか確認しやすいからです。
新聞紙は湿ってくるので2、3日ごとに乾いた新聞紙と取り換えてください。30日を過ぎると甘みが減ってしまいますので、30日以内に食べきりましょう。
栗は0度に近いと甘みを内に蓄える性質があります。そこで近い環境のチルド室に置いて甘さを増やすのです。
私はどうせ食べるなら甘い栗のほうが好きなので、チルド室で4週間待とうと思います。
栗の皮をむく方法おすすめ3選!

面倒な皮剥きを楽にするため、簡単に皮が剥ける方法を3つ集めてみました。
【冷凍】
- 一晩栗を冷凍する。
- 一晩経ったらボウルに熱湯を入れ、栗を入れ5分待つ。
- 栗の平らなところをまな板につけ、栗のお尻側の皮に切れ込みを入れる。
- そのまま包丁で切れ込みをまな板側に押し付け、栗を上方向に上げていく。
まだ剝いてない栗は湯につけておき、栗が温かいうちに剥いていきます。包丁で切れ込みを入れた後は手で毟るように剝がすこともできます。
【熱湯】
- 洗った栗を用意し、尻側に切れ込みを付ける。
- ボウルに熱湯を張り栗をすべて入れる。
- ラップをかけて10分放置する。
- 10分後、切れ込みから皮が剥ける。
電子レンジでのやり方は栗が少量の時にお勧めです。
【電子レンジ】
- よく洗った栗を用意し、栗の尻側に切れ込みを入れる。
- 耐熱容器に5個くらいの栗を入れかぶるくらいに水を入れる。
- ふわっとラップをかけ、600Wで1分30秒レンジにかける。
- 出来たら、切れ目から剥く。
従来の、長時間茹でる方法に比べて短時間でできる栗がむきやすくなる方法をご紹介しました。
これで皮付き栗が家にあっても調理が億劫になりませんね。
私はレンジでの調理法を試してみたいと思いました。少量の栗を食べるだけなのに鍋を出すのがためらわれますが、これからは栗を買っても簡単に調理できるので安心です。
栗の栄養素は葉酸やビタミンCなどたくさん

私は、栗について、なんとなく芋やカボチャの仲間のような印象を持っていました。そこで、栗に含まれる栄養素を調べました。
<栗の栄養素(可食部100gあたりの量)>
| 栗(なま) | 栗(茹で) | |
| エネルギー(kcal) | 147 | 152 |
| タンパク質(g) | 2.8 | 3.5 |
| 脂質(g) | 0.5 | 0.6 |
| 炭水化物(g) | 36.9 | 36.7 |
| カリウム(mg) | 420 | 460 |
| 鉄(mg) | 0.8 | 0.7 |
| ナイアシン(mg) | 1.0 | 1.0 |
| 葉酸(mg) | 74 | 76 |
| ビタミンC(mg) | 33 | 26 |
| 食物繊維総量(mg) | 4.2 | 6.6 |
文部科学省食品成分データーベースによると、おにぎり100g分の炭水化物の量が約39.4kcalで、栗100gで約36.9kcalなのでほぼ同じ量となります。
栗は案外カロリーが高いので、あまり食べ過ぎると太りそうで心配ですね。
また、栗に多く含まれているカリウム、葉酸、ビタミンC、食物繊維のそれぞれの栄養素の役割などを紹介しますね。
【カリウム】
農林水産省によるとカリウムは体にある余分な塩分を排出する役割があります。
通常の食事ではカリウムが大幅に不足することはないとされています。
しかし、カリウムが不足すると、筋力の低下、筋肉の痙攣や麻痺、不整脈が起こる可能性があります。
カリウムの一日の目標摂取量は、18歳以上の男女それぞれ3000mg以上、2600mg以上となっているので、サプリなどでもカリウムを摂っている方は摂り過ぎに気を付けてくださいね。
【葉酸】
葉酸は女性に嬉しい栄養ですよね。鉄と葉酸がセットになっているサプリメントもあります。
健康長寿ネットによれば葉酸には赤血球を作る造血作用があります。核酸やたんぱく質の合成を促進したり、細胞の生産や再生に役立ちます。
胎児の発育に重要な栄養素なので、妊娠前から産後にかけて摂取することが良いというのは聞いたことがあるのではないでしょうか。
【ビタミンC】
厚生労働省のホームページによるとビタミンCは、皮膚や粘膜の維持に役立ち、抗酸化作用を持ちます。免疫力向上やストレスに対する抵抗力を強める作用があります。
ビタミンCは水溶性なので、摂りすぎる心配も少なく積極的に摂りたい栄養です。
【食物繊維】
農林水産省によると食物繊維は、整腸効果や便秘の予防に有効です。特定保健用食品で「おなかの調子を整える食品」と認められている成分の多くが食物繊維です。
便の体積を増やす材料になったり、大腸の環境改善する腸内細菌に利用され菌を増やすとされています。
栗には抗酸化作用や造血作用など、特に女性が取ることが望ましいとされている栄養がたくさんありましたね。私も栗を食べる回数を増やそうかと思います。
まとめ

- 栗は洗った後に半日から1日程度水につけておくと良い。水につけることで硬い皮が柔らかくなり、剝きやすくなる。
- 水に浮く栗は虫が食べている。変に黒かったり、穴が開いている栗も虫に食べられているので捨てること。
- 皮に艶があり光沢のあるもの、重さを感じ、丸みがあり粒が大きい栗を選ぶといい。
- 栗を水につけるもう一つの理由は虫を追い出すためで、よりしっかり虫止めした場合は、80℃くらいのお湯に栗を二分間入れる。
- 栗の汚れを拭き、天日干しにすると甘みが出てくる。
- 洗って水けを取った鬼皮付き栗は、新聞紙かキッチンペーパーに包み、ポリ袋や保存袋に入れて4週間チルド室で寝かせると甘くなる。
- 冷凍、熱湯、電子レンジを使って栗の皮を剥きやすくしよう。
- 栗はカリウム、葉酸、ビタミンC、食物繊維など栄養がたくさんある。
栗を買ったりもらったりしたとき、洗ってから水につける下処理をすることがわかりました。その理由も、皮を柔らかくするためと虫を追い出すためということでした。
今まで教えられてなんとなく行っていたことにちゃんと意味があったと知ると驚きますよね。
私は皮付きの栗は剥くのが大変で、手が痛くなっていましたが、今回簡単に皮が外れる方法を知って試してみようと思いました。
いつも食べている剥き栗ではなく、皮付きの栗を調理してみると新しい美味しさを発見することができるかもしれませんよ。